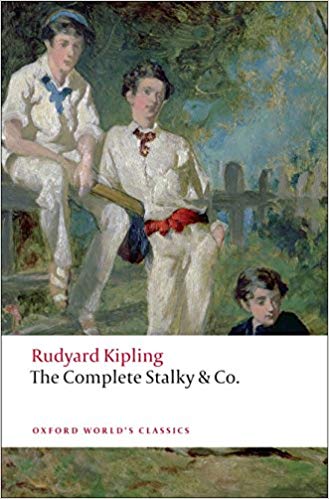第6話 「偉大なるストーキー」 その1
『海山物語』
(ラドヤード・キプリング著 マクミラン発行 1923年初版 1951年再編集版) 底本 Land and Sea Tales for Scouts and Guides by Rudyard Kipling MACMILLAN AND CO.,LIMITED 1951 (First Edition November 1923)
(訳者より)
今回からはパブリックスクールの男子3人組のお話。
作者キプリングの実体験をもとにした物語です。
19世紀イギリスのパブリックスクールというと上流階級の寄宿学校のイメージですが、 この3人が所属するのは United Service College (総合軍学校)。陸軍または海軍の士官学校を目指す、中流階級の子弟向け寄宿学校です。
キプリング自身も Beetle という名前で登場します。日本語でビートルというとちょっとカッコいいイメージですが、実のところ運動は苦手で度の強いメガネをかけているがゆえのあだ名なので、「カナブン」と訳してみました。
このお話の続編は『Stalky & Co / ストーキーと仲間たち』というシリーズものになっていて、かなりの人気を博し、テレビドラマ化もされたようです。)
(著者キプリングの前書き)
これは、3人の男子学生――「ストーキー」、マクターク、「カナブン」の冒険と行動をつづる最初の物語となっている。 いくつかの理由で、彼らの冒険物語集である『ストーキーと仲間たち』に収録されることはなかったものだ。
遺憾ながら、この物語のかなりの部分は事実に基づいており、推奨すべきものでもないが、私はその中に一つの教訓を見る。
それは、いかなる理由であれ、苦境に陥った時には、熱くなるよりも冷静である方が、楽に切り抜けられる機会を得られるということだ。立ち止まって考える方がよいのである。
雨の中の少年たち
「それでだ」 と、いやに冷静で落ち着いている少年の声。
「デ・ヴィッレは、俺たちが救いようのないビビリの臆病者だって言うのさ。
俺は、そいつは相手が多すぎて、俺たち向きじゃあないって言った。
ついでに、デ・ヴィッレがよこす件にはあっちこっち面倒があるとね。
違ったかな、カナブン?」
「まあ、とにかく、ふざけた仕事だよ、まるっきりね。
あいつら、そのどうしようもない牛たちを手に入れて、どうするつもりかな?
1頭ならミルクをしぼれるんだけど――牛がじっとしてくれてればさ。
それはそうとして、牛たちを引き連れていくとなると――」
「お前はブタかよ、カナブン」
「違うよ。何をしたいのかなって、バロウズから牛の大群を連れ出して――
えっと、どこへ行くんだっけ?」
「牛を追い立てて、丘のてっぺんのトゥーウェイの農作業場――
火曜に俺たちが一服した、からっぽの農場へだ。
恨みを晴らそうってのさ。
先週、ヴィドレーのおっさんが2度もデ・ヴィッレにうるさく言ったんだ。
バロウズの農場で自分のポニーに乗ったからってな。
それでデ・ヴィッレはヴィドレーの牛をできるだけ追い上げて、丘の上に移しちまうつもりなんだ。
パーソンズ、オリン、ハウレットに手伝わせる気だろうが、あいつら、ただ叫んでわめくだけで、ヴィドレーを見たら逃げ出すな」
「オレたちなら、うまくやれたかもなあ」
ゆっくりとマクタークが言った。
バロウズを洗う雨をしのごうと、コートの襟を立てる。
彼の髪は、その癇性にふさわしく、暗い赤褐色だ。
「やれるさ」とコークランが同じ悠長さで答えた。
「だが、あいつらはスズメ狩りでもやるみたいに事を始めちまった。
俺は牛泥棒なんてやったこともないが、何にせよ「ストーキー」になるにこしたことはないと思うね」
大西洋の水蒸気が雲となって、少年たちの頭上を走る。
霧の中から風を貫き、ペブル・リッジの灰色の砂洲の彼方、1マイルにもおよぶ大西洋の巻波の咆哮が、絶えず響いてくる。
風下に向かって、はぐれたポニーと牛が数頭、煙霧の中から姿を見せた。
ノーサムの家長らの所有だが、心ならずも、ヒマな少年たちの慰み者にもなる家畜たちだ。
牧場門のところで、3人の少年がたたずんでいた。
そこは耕作地の終わりの目印で、ノーサム丘からバロウズへ牧草地が広がっている。
くしゃくしゃ頭にメガネの少年、カナブンは濡れた柵の横木に沿って、あちらこちらへ鼻を動かす。
マクタークは、片方の脚からもう一方へ体重を移し、水がどちらの足跡に流れ込むのか見ている。
一方、コークランは芝の土手に寄りかかって歯笛を吹きつつ、霧の向こうを凝視していた。
成熟した、あるいは分別のある人物ならばこの空を荒天と呼ぶだろうが、かの学校の少年たちは、天候に関する国家的重要性についてはいまだ学んでいなかった。少々湿り気があるのはわかっているが。
とはいえ、復活祭の時期(※)がじめじめしているのはいつものことで、海からの湿気にも彼らは耐え、どんな環境でも風邪ひとつ引くことはなかった。
レインコートなどは教会に行く時のもので、荒れた土地で急ぎ走らねばならない場合には邪魔になるだけ。
だから3人はどしゃ降りの中、母親なら見たくないであろう姿で平然と待っていた。
(※3月)
「ねえ、コークラン」とカナブン。
彼がメガネをぬぐうのはこれで12回目だ。
「ぼくらがデ・ヴィッレを手伝わないんなら、何でここにいるんだい?」
「見張ってるんだ」というのが答えだった。
「状況をよく観察するんだ、そうすれば運が向いて来る」
「ひっでえ仕事だよな、牛追いなんざ――
それも丸見えのところでだぜ」とマクタークが言う。
彼はアイルランドの准男爵の息子だったので、こういう仕事には一家言あるのだ。
「あいつら、牛を追ってバロウズを半分も走るはめになるぜ。
ヴィドレーのポニーに乗る気かな?」
「デ・ヴィッレはその気だろう。
ヤツは乗馬が得意だからな。
聞こえるだろ、あいつら、ひどい音を立ててる。
何マイル離れてたって気づかれるぞ」
デ・ヴィッレ、牛を追って駆ける
喚声、雄叫び、金切り声、指図、壊れたゴルフクラブのガチャガチャ音、馬蹄の響きが大気に満ちる。
3頭の牝牛が子牛ともども、牧場門のところまで駆けて来た。
後に続くのは、猛った眼つきの牡牛4頭に、毛の長いポニーが2頭だ。
それを追って、太ってそばかす顔の15歳の少年が裸馬に乗り、棒杭を振り回しながらやって来る。
デ・ヴィッレは、馬の訓練に関して情熱を持っており、この点については才気ある若者であった。
もっとも、それはノーサムの農民が奨励するものではなかった。
農場主のヴィドレーは、放牧地のポニーが速駆けさせられるのが好きだなんて理解できず、以前デ・ヴィッレのことをコソ泥と呼んだことがあった。
その侮辱が恨みとなっての、この強奪である。
「来いよ!」デ・ヴィッレは肩越しに叫んだ。
「門を開けろ、コークラン、
でなきゃあ、牛どもがみんな引き返しちまう。
連れ出してくるのにさんざ苦労したんだ。
ヴィドレーの野郎、怒り狂うぜ!」
3人の少年が走って追いついて来た。
シーッシーッと素人ながら躍起になって牛を追い、高い土手沿いの狭いデヴォンシャー路へ導き、丘の上へ向わせる。
「来てくれよ、コークラン。
お楽しみはこれからなんだぞ」とデ・ヴィッレが懇願した。
だが、コークランは首を振る。
あの晩、夕食の後で切り出されたこの仕事はすっかり計画が出来上がっており、ひいき目に見ても、コークランの役は大したものではなさそうだった。
そして学籍番号104番、アーサー・ライオネル・コークランは副官の役に興味はなかった。
「捕まるのはお前だけだ」
とコークランは叫んで、門を閉じた。
「パーソンズとオリンは物の数じゃあない。
お前は確実、捕まるよ、デ・ヴィッレ」
「このビビリの臆病者め!」
そう言ったかと思うと彼は霧の中へ消えて行った。

「ストーキー」さが足りない
「ちきしょうめ」とマクターク。
「ウチの学校で初めて牛追いをやれたかもしれねえ。なあ――」
「冗談じゃあない」とコークランは断固として言う。
「状況をよく観察するんだ」
こういう場合、彼の言葉は絶対だった。
これまでの経験上、コークラン抜きで冒険を試みても、ひどい目に遭うばかりだったからだ。
「今回のは自分が考え出したんじゃないから、気に入らないんだろ」とカナブン。
コークランは彼を軽く3度蹴りつけたが、2人ともケンカ腰になったわけではない。
「違うね。
俺から見ると「ストーキー」さが足りないのさ」
「ストーキー」とは彼らの学生言葉で、行動を計画するにあたって、賢い、思慮深い、策略に富むことを意味する。
そして「ストーキーさ」はコークランが求めてやまぬ一つの徳なのだ。
「違わねえよ」とマクターク。
「ウチの学校で「ストーキー」なのは自分だけだって思ってんだぜ」
コークランは、カナブンに対してと同様に彼を蹴った。
だがカナブンと同じく、マクタークは少しもそれを本気に取らなかった。
3人の友情の上では、ある提案についての正当な異議申し立てに過ぎなかったからである。
「あいつら、偵察をまるで出さなかったろう」コークランが続ける。
(彼らの学校は、陸軍向けに生徒を鍛えていた。)
「出すべきなんだ――リンゴを取る時でもな。
トゥーウェイの農作業場は、農夫のおっさんだらけかもしれない」
「1週間もたたないよ」とカナブン。
「荷馬車小屋で一服した時からさ。
どの家からも1マイルは離れてるし」
コークランの淡い眉が片方上がる。
「ったく、カナブン、お前を蹴るのもうんざりだ!
今もその小屋に誰もいないってのか?
仲間の1人でも見に行かせるべきなんだ。
あいつらはきっと捕まる。
逃げるとしても、どこへ隠れる?
パーソンズはこっちに来てまだ2学期、この辺りの地勢を知らない。
オリンはデブで、ハウレットは見当たる限りの治者(※)から逃げることになる。
デ・ヴィッレだけはまあ、相当なものだ――
それで、俺はヤツをトゥーウェイの農作業場に行かせた」
(※ 農業に従事するデヴォンの地元民を指す方言)
「ええと、怒らないでよ」とカナブン。
「僕ら、どうするんだい? この辺、もうぐしょ濡れだよ」
「ちょいと考えるんだ」
コークランは歯笛を吹き、素早く短い音を2度入れた。
「丘に上がって、あいつらがどうなるか見てみよう。
牧草地を渡って、納屋のそばに路が続く辺りの生垣に隠れる。
前学期にヤマアラシの死骸を見つけたところだ。
行くぞ!」
もはや手遅れ
彼は土手をよじ登り、雨に濡れた犂の上に跳び降りた。
そこは急坂で、トゥーウェイの納屋のある丘の頂上へ続いている。
3人は踏み段や歩道には目もくれず、牧草地の中を対角線に突っ切り、生垣を見つけるとビーグル犬よろしく潜り込んだ。
路は右側に伸びており、そちらから牛の声や人の叫びが大きく聞こえてくる。
「ふーん、捕まってなけりゃ」
マクタークはそう言って、門柱に向かって泥を少し蹴り飛ばした。
「デ・ヴィッレは大はしゃぎに違いねえな」
3人は、古びて隙間のある二重の生垣の一番端まで進んだ。
そこは、四角いガレージの付いた大きく黒い木造の納屋から30ヤードと離れていない。
10分ほど登っていくことで、3人はバロウズの上、200フィートまで来た。
こちらとバロウズの方を霧が分かつと、濡れた緑の大三角が見えてくる。
そこには黄色い砂の丘が点在し、縁には白い泡が巡る。
ぼんやりした地図が眼下に広がるごとくである。
ペブル・リッジの大波の響きを背景に、路には野卑た声が満ちていた。
「言わんこっちゃあない」
コークランは、サンザシの生垣越しに農作業場を見渡した。
「3人のオッサン、肥しを運んでたのか、熊手を持ってるぞ。
デ・ヴィッレを止めるのは手遅れだな。
出て行ったら、俺たちも捕まる。
ってか、オッサンたちはあの音を聞いてる。
聞こえないはずがない。バカめ!」
土地の男たちは武器を振りたてつつ、話し合っていた。
「寮生」という言葉が何度も飛び交う。
騒ぎが近づいて来ると、彼らはそれぞれ柵囲いや小屋に姿を消した。
最初の牝牛が作業場の門を駆け抜け、デ・ヴィッレは仲間に声をかける。
「上出来だ」と彼は叫んだ。
「あ~あ、ヴィドレーのジジイはカンカンだろうぜ!
門を開け放てよ、オリン。鞭をくれて通させるんだ。
牛ども、かなりカッカきてるぞ」
「もうすぐお前がそうなるんだよ」
マクタークがつぶやいた。
泥棒たちが牛の後から、作業場へ走り込む。
勝利の雄叫び、そして絶望の甲高い悲鳴。
地元の男が1人、熊手を持って門を固め、あとの2人が、残念、少年4人を全員捕らえた。
「全員、どうしようもないバカの劣等生だな!」とコークラン。
「あいつら、制帽すら脱いでない」
このくちばしの黄色い、甘ちゃんのボンボンたちには、同窓の誇り、愛校心を鼓舞することの意味が教えられていなかった。
だが、遠くからでも自らの所属を示すため、制服の着用者は限界や法を超えるべきなのだ。
だからこそ、戦時には愚か者以外、誰も軍服を裏返しに着ないのである。
「よお! いたずら小僧ども。捕まえたで!
ヴィドレーさんの牛に何かあったんかいのう?」
(続く)