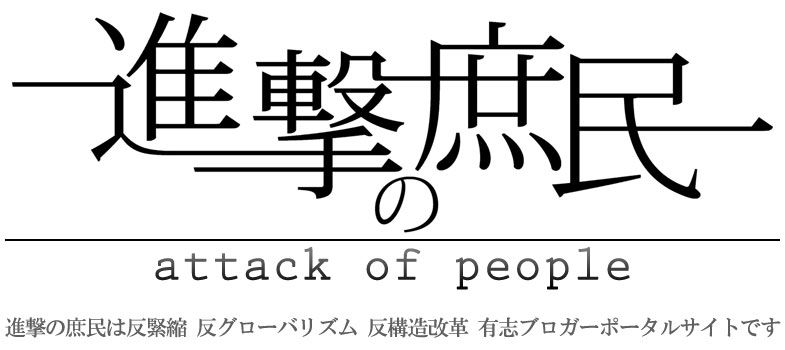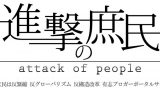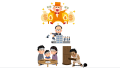経済のインフラとしての貨幣
貨幣は、発行されるだけでは価値を持ち得ず、逆に価値があっても流通していなければ、その価値を発揮できません。
貨幣を経済のインフラとして位置づけて考えるのであれば、まず貨幣価値を担保すること、そして貨幣を流通させることが必要になります。
貨幣の価値を担保するには、モノやサービスに対して貨幣の価値を維持、つまり過度の物価上昇を抑制しつつ、貨幣の流通を加速、即ち賃上げや設備投資により消費を促さねばなりません。
貨幣が金融に回り過ぎれば、例え発行されても必要な実物投資や消費に回らず、一部の投資家の証券投資やマネーゲームに浪費されたり、一部の資本に溜め込まれて流通しなくなってしまいます。
要するに貨幣とは、経済を回すための重要なインフラの一つであり、私たち庶民にとってはそれ以上でもそれ以下でもありませんが、これが資産と言う間違った視点でのみ語られたとき、貨幣の重要なインフラとしての役割は失われてしまう、つまり、貨幣が貨幣として機能しなくなってしまい、実質的にその価値を発揮できなくなってしまうわけです。
多数派のための経済と昭和の資本主義
多数派のための経済というものを資本主義的な文脈で考えるとき、単に税制度や財政政策という枠内だけでは達成は難しいもので、経済の土台となる慣習や風土といったモノまでが、ある一定の方向に向いている必要があります。
それが理想的な方向に向いていたのが、昭和の資本主義でした。
昭和の修正資本主義下では、株の持ち合いによって株所有者は他でもないその企業の取引先企業であり、実体経済における関係性が重視されることで株主至上主義特有の利益最大化・コストカット経営は最小限に抑制され、企業は個人の所有物ではなく、一種の社会資本に限りなく近いものとして機能していました。

しかし、バブル崩壊以降、グローバリズムによって、そういった経済風土や慣習は破壊しつくされ、今では瓦礫すら残されておらず、株主至上主義による一部の者が富を独占する“少数派のための経済構造”が構築されてしまいました。
少数派のための経済構造、即ち株主至上主義的経済構造の文脈上でしか経済を、財政を語ることが出来ない状況で、果たして多数派のための経済を実現することが可能でしょうか?
そんなものは、不可能に決まっています。
現状とは異なる経済構造の構築を議論しなければ、現状は打破できません。
幸いなことに我々日本人は、昭和の資本主義という、企業が株主支配よりも限りなく社会資本に近かった時代を、歴史として内包することが叶うという幸運に恵まれました。
モデルケースは、既にあります。
現状追認、認知的不協和に陥らず、現状を分析しながら理想に近づく議論をする土台は、既にあるのです。
無論、その人がどのような経済を、社会を、国家を志向するのかは、個人によって異なります。
現状追認、株主至上主義に則った現状のままを望むのならそれもいいかも知れません。
その結果が亡国に至るとしても、今の世代が居なくなったあとのことです。
その代わり、ツケは文字通り、将来世代に回って来ます。確実に。
温故知新と新しい経済構造の構築
新しいものだけを求め、過去を歴史を顧みない姿勢は、今のところ全てが裏目に出ています。
日本が近代化する過程で、日本の古来からある固有の文化と、欧米文化との絶妙なハイブリッドは、日本に黄金時代をもたらしました。
しかし、その時代を過ぎた今、日本は欧米の文化を過剰摂取することで中毒症状を起こしてしまっているのです。
その毒を中和していくためにも、温故知新、古きを再び温め直して、これから必要な新しい知見を築き上げる必要性が、今こそ必要なのではないでしょうか。