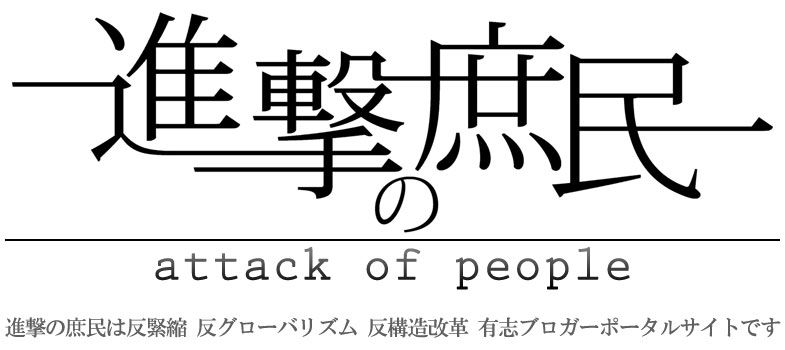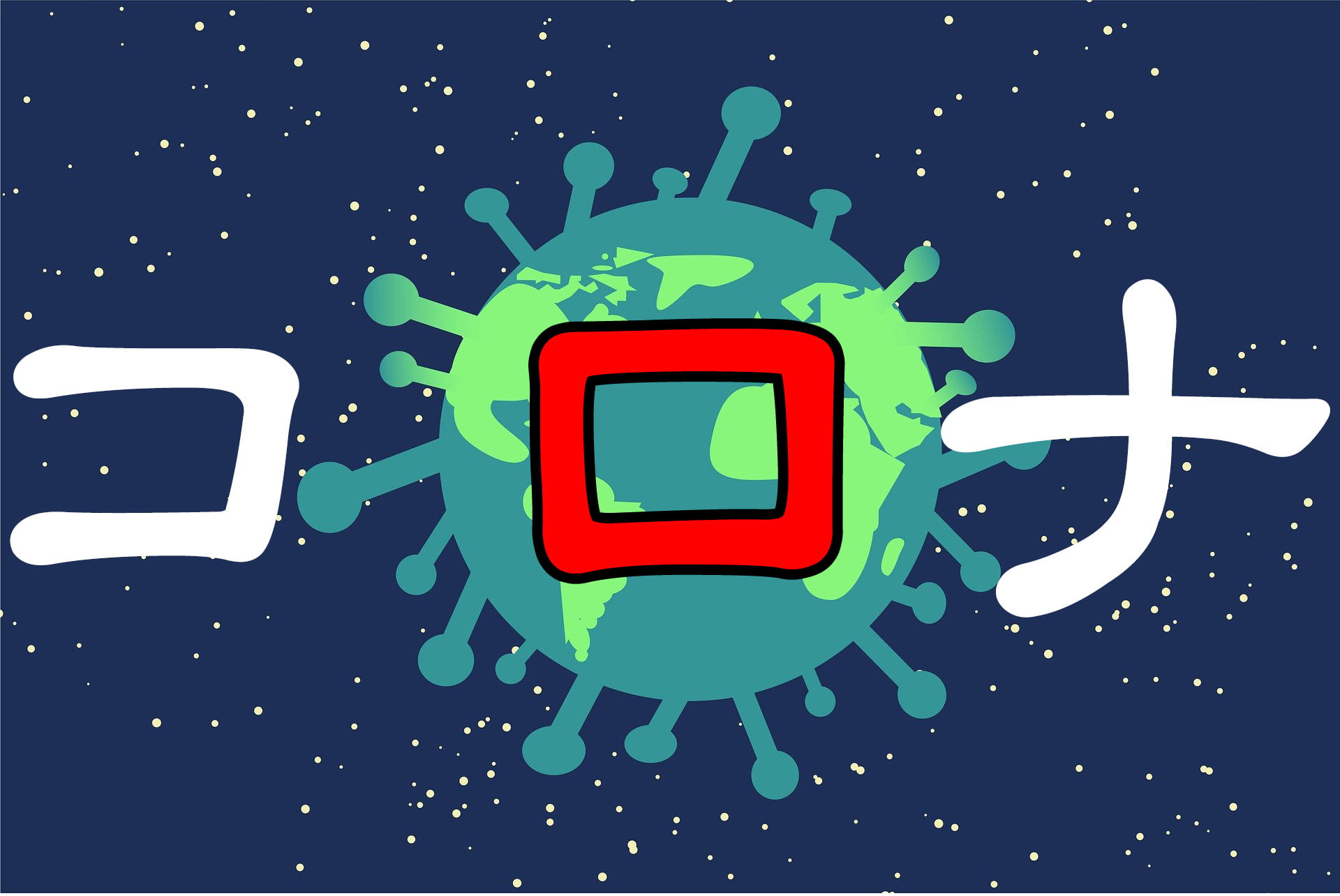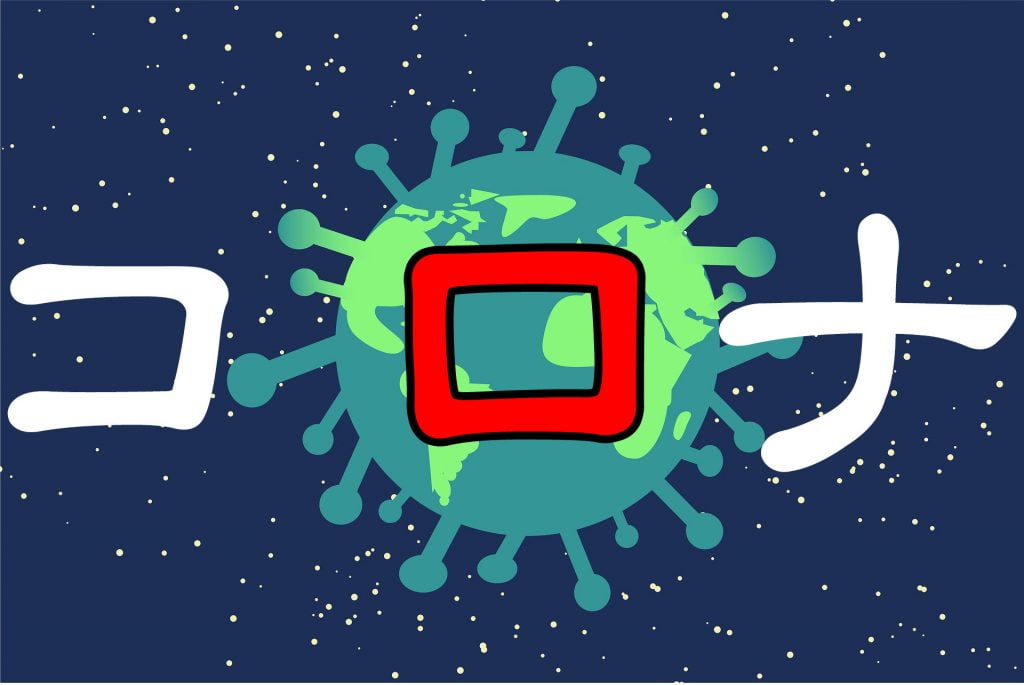
自粛要請という言葉は不思議ですよね? もし不思議に思わないのであれば、きっと「強制ボランティア」や「強制連行」という言葉も不思議に思わないことでしょう。
ボランティアって強制されるものではありませんし、連行はそもそも強制ですよね。全く同じように自粛要請も不思議な言葉なのです。
言葉としてねじれている自粛要請の効果が低下しています。その理由について考えてみました。
自粛要請は意味が混乱する言葉
そもそも論として「自粛要請」という言葉は、意味が混乱しています。
自粛とは「自らつつしむこと」であり自立的な言葉です。「今は喪に服してお酒を自粛する」とか「天災で大変なので、お祭りを自粛する」など自分を起点とした行動が自粛です。
すなわち自粛は自律的な言葉です。
一方で要請とは「強く願い求めること」です。「外出を控えるように要請する」「自衛隊の救助を要請する」など他律的な言葉です。
本来、自粛と要請はセットになりません。強制とボランティアがセットになって「強制ボランディア」となると「それ、もうボランティアちゃうやん!」と違和感を抱きますよね。
自粛と要請も「要請されている時点で自粛ちゃうやん!」。
自粛要請という言葉は不思議でどうとでも取れる言葉です。
一方で、政府にとってはあくまで「自粛してほしいとお願いしているだけ」ですから、自粛するかどうかは自己責任。自粛して飲食店がつぶれても自己責任です。
このあたりのねじれも意識しつつ「自粛要請の意味が薄れてきている」という議論を展開します。
自粛要請や時短要請は意味があるか
自粛要請や飲食店への時短要請はコロナの抑制に効果的なのでしょうか? 「あれだけ頑張って自粛したんだから効果的であってほしい」と思うのが人情でしょう。
「夜の街」時短要請効果あった? 第2波の時のミナミは [新型コロナウイルス]:朝日新聞デジタルによれば、確かに時短要請や自粛要請は効果を発揮しています。
記事によればこうです。
民間会社のデータを元にした別の府の分析では、2週間の要請期間中にミナミの難波地域の夜の人出は7月と比べて8割程度に減った。大きな効果が出た。他の繁華街でも減っており、相乗的な効果がある。
コロナ第2波のとき、大きな効果がありました。
しかし休業協力金などの保障が不十分で、飲食店は悲鳴を上げています。時短要請や自粛要請はあくまで「お願い」です。
応えるかどうかは「自己責任」ですから、保障も不十分なものにならざるを得ません。
自粛要請の効果が薄れてきている?
こういった状況の中で我が大阪に赤信号がともりました。
大阪府は12月5日に不要不急の外出自粛要請が出され、営業時間短縮要請も11月27日から出ています。
まさに戒厳令といった感じですが――繁華街の人手は「少し減ったくらい」と報じられています。
参照 大阪「赤信号」でも「要請は気にしない」観光客らの姿も – ライブドアニュース
記事によれば「要請を気にしない」という観光客もチラホラいるようです。
何度も保障なき自粛要請を重ねた結果、「保障がない」「慣れた」「そう何度もやってられない」と思うのもまた人間です。
徐々に自粛要請の効果が低下して、自粛要請が意味をなさなくなってきています。
この現象はおそらく、大阪だけにとどまらないでしょう。
まとめ
自粛要請という言葉はねじれています。意味が混乱しており、非常に不思議な言葉です。
要請なので応えなくていいのか、それとも応えなければいけないのか。わかりづらいですよね。
「自粛をお願いされているだけ」なので、筆者はあまり自粛してません。
コロナ疲れもあり今後、そういった人たちは加速度的に増えていくでしょう。すなわち自粛要請の意味がなくなり、効果が低下していくと思われます。
政府はコロナ禍に対応するため、自粛要請ではなく「時短命令と粗利保障」「外出禁止令と休業補償」など、しっかりとねじれていない対策を取るべきです。