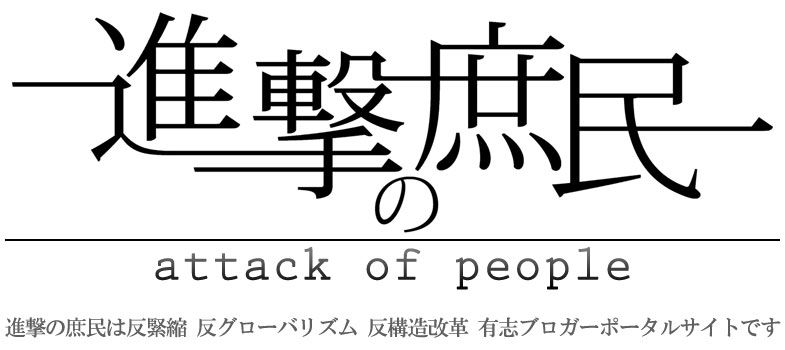先週、三橋経済塾の福岡講演および懇親会に参加してきました。グローバル資本主義の害を抑えるためにぜひとも必要なものが、共同体意識/ナショナリズムです。これを広げるためにはどうすればいいのか? キーワードは「ヤンキーとエリートと楽しさ」。講演と懇親会での議論体験から考えてみます。

ヤンキーとエリートと共同体意識
講演会は三橋貴明さんの講義と施光恒教授の講演の2本立てでした。
三橋さんの講義タイトルは「共同体と資本主義」、施さんのは「ナショナル派とグローバル派」。
三橋さんは主に経済面から、施さんは政治面から、と角度を変えてですが、奇しくもその趣旨は同じ。
グローバリズムが引き起こす問題を解決するには、ナショナリズム/共同体意識が必要ということでした。
そこで私、最後の質疑タイムで挙手。
「エリート層には、小中学校でスクールカースト下位に甘んじ、ヤンキーからひどい目に遭わされるなどして、共同体なるものがイヤになった人が多いと思われます。
そんな彼らは高校受験、大学受験を経て地元共同体の縛りを抜け出し、エリート層/エニウェア族の生活で幸せを得ているわけで……
そんなエリート層が共同体意識に目覚めるには、何が必要でしょうか?」
お二人からいただいた回答の趣旨は以下のようなもの。
1 読書や生活の体験の中で個々が気づいていく。
2 一気に共同体意識に目覚めるのは、戦争などの大きな危機の時。
なかなかきびしいですね……。しかし、だからこそインターネット上などでの言論活動、情報拡散が大切だということでもあります。
ヤンキーと町内会と地方行政
ヤンキーがあらわれた!
講義の後は懇親会に参加しました。
九州のみならず、本州・東日本から来たという方もいてちょっとびっくり。
そんな中に私と同郷、しかも1歳差の方(以下、Aさん)がいまして、
私「中学どこでした?」
Aさん「○○中です」
私「ああ! うち▲▲中」
Aさん「ワルいとこのトップ2がそろってるやないですか!」
私「ヤンキーが幅きかせてましたね。モテるのもヤンキーばかり」
Aさん「生徒会もヤンキーでしたよ。在任中に警察につかまりましたけど」
私「そりゃ衝撃ですねー。あと、カツアゲとかもやられましたねえ、あれはキツかった」
Aさん「僕なんか近所の山道歩いてたら、いきなりヤンキーが出て来てカツアゲされましたよ」
私「山賊かよ!?」
町内会/自治会と地方行政
というわけで、私を含めて必ずしもエリートに限らず、ヤンキー被害のせいで共同体に忌避感を覚える人は多そうですが、それでも町内会などに参加する人もいます。
ちなみに、町内会や自治会というのは、地方行政に大きな影響力を持ちます。
地域住民の意志を束ねる強力な中間団体です。
ここの力が強くなれば、いわゆる都構想や外国人地方参政権など、地方行政での暴挙を止められるとも思います。
丸くなったヤンキーは好人物に?
私
「地域にもよると思いますけど、意外と自治会活動とかって参加してみると楽しいんですよね。
マイルドヤンキーというか、昔ワルかったような人も、地元愛を持ったまともな人になってて普通につき合えることもあるし」
Bさん
「そうですね。うちの町の役員には元・暴走族がいますよ。
警察がワナ張ってるところにバイクで突っ込んで、コケたところを捕まったとか……。
今はまったく気のいい、頼りになるおっちゃんです」
ヤンキーだって、いつまでもトガっておらず、成長と共にマイルドになる。
その快活さや交遊の広さから地元共同体で活躍することも多い。
ヤンキー時代の彼らを知らない者にとっては、単純に好人物と見えましょう。
仕事の都合などで実家/故郷を離れて生活している場合の方が、むしろ町内会・自治会活動に参加しやすいかも知れません。かつてのスクールカーストと無関係に、イチから参加できるのですから。
楽しい体験が、共同体意識に目覚めるチャンスをつくる
お祭りで目覚める
MBA取得済みで割と「グローバル寄り」だと言うCさんは……
Cさん
「以前赴任先の土地で、すごく伝統あるお祭りに参加することになったんですが……
タテの上下関係とか厳しいし、練習とかハードだし、面倒でムチャなこともあるんですけど楽しかったんですよ、ホントに。
きっかけは会社命令とはいえ、やってよかったなと。
それで伝統とか共同体っていいものなんだと思ったんです。
仕事・ビジネスばかりじゃ良くない。それで今日の講演会にも参加したわけです」
私の校区のもちつき大会にも例年、地元企業の社員さんが参加してました。
和気あいあいと一緒に杵を振るい、つきたてのもちを食べる。
共同体なるものの良さを彼らが感じ取ってくれていたらうれしく思います。
(コロナ禍の今年は、もちつき中止なのがイタいところ……)
政治団体/国守衆の楽しさ
国守衆に入っているというDさんは、
「和歌山に行って、二階俊博事務所前で街宣活動やったんですけど、すごく楽しかったです。
一緒に歩いて、声を上げて。事務所は無反応でしたけど」
こういう政治団体も共同体の一種でしょう。
二階氏らのチャイナ売国は許しがたく、この活動はありがたいところ。
違いを忘れて一体となる楽しさ
思いを共にする
政治団体には、その志に賛同して参加するわけですが、それでも参加者の間に違いはある。
新型コロナを心配する人、心配し過ぎと思う人。
トランプ再選を願う人、バイデン確定と思う人。
今の若者は苦労し過ぎと思う人、苦労が足らぬと思う人。など
それでも「日本を良くする」という思いを共にして行動する、細かな違いを忘れて一体となる。
だから「楽しい」。
自治会・町内会の地元共同体だと、人々の間の違いはもっとあります。
「政府はムダをけずれ」「消費税は仕方ない」
「グローバル化も仕方ない」「日本は人口が減るから成長しない」
すべて大間違いのとんちんかんですが、それを面と向かって議論して修正するのは難しい、というかかなりムリ。顔を合わせるとモヤモヤがたまります。
とはいえそんな相手でも町を良いところ、住民が安心して暮らせるところにしたいとは思っている。
その気持ちを共有して、地元の祭りやイベント、清掃活動や見回りなどをする。
地元の行政について話し合う。違いを忘れれば、楽しく役に立つ働きができます。
楽しさは人を呼ぶ
そして楽しいところには人がやって来る。参加する人が増えます。共同体意識に目覚める人が増えるわけです。
面倒なこともありますが、これは施さんと三橋さんの言う共同体意識に目覚める機会、
1 読書や生活の体験の中で個々が気づいていく。
これを援助するものと言えましょう。
地道な努力ですが、日本のナショナリズム/共同体意識の復活には大切な努力だと思います。
今回の懇親会では本当にいろんな方々とお話しできて楽しかったです。
また機会がありましたら、一緒に飲みに行ければと願っています。