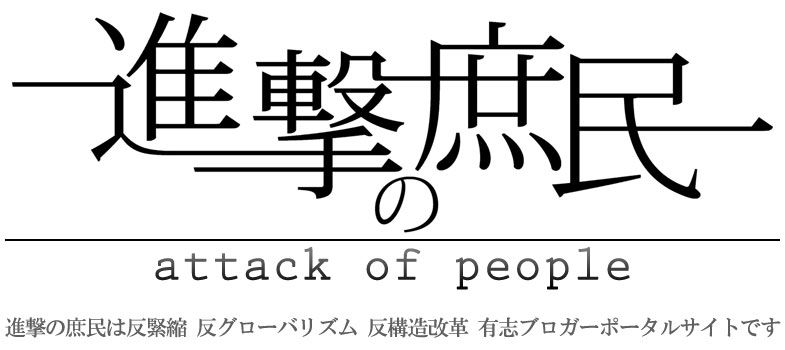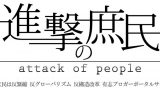日本がデフレに突入して、すでに20年以上が経過しています。失われた20年は、失われた30年になりかけです。
世間的にもデフレという単語は、一般化しました。ネットでググれば解説も出ています。
ところがデフレマインドでググったところ、ろくな解説がありません。一般的に表現して正確ではない、悪く言えば「嘘」です。
正しい情報や解釈なしに、正しい判断がなされることはあり得ません。どこにも書いてないのでしょうがなく、正しい「デフレマインドの意味」を解説します。
デフレマインドの意味とは
デフレマインドとググって出てくる解説を、2つ引用します。
デフレマインド
別名:デフレ心理
英語:deflation mindset、deflationary mindset長期にわたるデフレ(デフレーション)を経て世間に浸透し定着してしまった考え方、心理状態、消費の傾向などを指す語。
たとえば、余分な出費は極力減らして、必需品も安物を選び、手元に残った資金は将来のために貯蓄する、という生活様式はデフレマインドの典型例といえる。デフレ経済のもとで消費活動を抑制し、安い商品を求める。企業側も商品を安く売るために人件費を設備投資を削減し、さらに収益を将来のために留保する。そうした考え方にすっかり染まってしまうと、少し景気が回復の兆しを見せても容易には財布の口を緩めない。景気回復が実感できないどころか回復する芽をもつぶしかねない。
デフレマインドは、2010年代半ば現在、デフレを脱却しつつある状況下で浮上してくる課題のひとつとしてしばしば言及される。
「デフレマインド」の意味や使い方 Weblio辞書
(2017年1月25日更新)
デフレマインド(でふれまいんど)
デフレマインド|証券用語解説集|野村證券
分類:経済
デフレ時代に染みついた企業や消費者の心理や行動様式。実体がどうであれ、今後も経済状況があまりよくないであろうと悲観的になる心理状態のこと。将来を不安に思い、節約や貯蓄をしてお金をあまり使わないようにしようと考えること。
どちらの解説にでも「実態がよくなっても、心理的に引きずって実態を悪くすることがある」というニュアンスで、デフレマインドが解説されています。
結論から書きます。デフレマインドは「失業率などと同じ遅行指数」であり「力学的な原因の結果に過ぎない」のです。
わかりやすく解説していきます。
デフレマインドと不況の因果関係と原因
デフレマインドは原因でしょうか? それとも結果でしょうか? 明確に「デフレになったから、デフレマインドが蔓延った」のであり「デフレマインドが蔓延ったから、デフレになった」わけではありません。
わかりやすい例を出します。「いじめに遭ったから、トラウマになった」のであり「トラウマがあるから、いじめられた」ではないのです。
デフレマインド・不況・政府支出の関係性
デフレの原因は、はっきりしています。政府支出の不足がデフレの原因です。この回答は主流派経済学であれ、現代貨幣理論であれ変わりません。
なぜなら主流派経済学も「政府支出が多くなれば、インフレになる」と認めているのですから、逆もまた真です。
とすると緊縮財政がデフレ状態を作り出し、デフレマインドの原因です。
デフレマインドは力学的な原因で発生し、力学的に対策可能
ネット上のデフレマインドの解説は、どれも「実態とデフレマインドという心理状態が乖離して、デフレマインドが実体経済の足を引っ張る」としています。
つまりデフレマインドを「精神的なもので、思い込みで解決できる」的ニュアンスで解説しています。
本当に?
貯蓄ゼロ世帯はデフレに突入してから、加速度的に増加しています。
貯蓄ゼロ世帯が1998年頃から加速度的に増加し、その間に国民の平均所得は50万円ほど下落しました。どう考えてもデフレマインドは、所得下落や貯蓄ゼロという「物理的要因」が原因です。
よって国民所得の向上などの「物理的対策」によって対応可能。
わかりやすく言えば「骨折しているのに、精神科に行っても無意味。外科でギブスをして治療しましょう」と一緒です。
デフレマインドは遅行指数であることは明白
景気が悪くなったと新聞で報じられてから、一般的な庶民が実感するにはどれくらいタイムラグがあるでしょう。失業率が上がった利所得が減少したり、リストラなどが横行して初めて「景気が悪いんだなぁ」と思います。
景気判断指数を見て、景気を実感する人などこの世にいません。
失業率やリストラ、所得の減少などは全て遅行指数ないし遅効性を持ちます。よって景気の実感と力学的要因に左右されるデフレマインドも、遅行指数の特徴があることは自明です。
多少景気がよくなったくらいで、デフレマインドが即解消されないのは「当たり前」なのです。
日銀の嘘「根強いデフレマインド」
デフレマインドは力学的であり、遅行指数であると述べてきました。問題解決は政府が、国民所得を向上させればすむ話です。
2018年9月の日銀金融政策決定会合における意見は典型的ですが、嘘にまみれています。
物価上昇の遅れは、単純な需要不足ではなく、根強いデフレマインドに加え、供給面の拡大による生産性向上など様々な要因に影響を受けることが判ってきており、先行きの物価を巡る不確実性は一頃より高まっている。
金融政策決定会合における主な意見(9月18、19日開催分) : 日本銀行 Bank of Japan
根強いデフレマインドとは何か? 賃金の下落などによる国民の貧困化が、根強いデフレマインドの原因です。日銀は「根強いデフレマインド」などと精神論に逃げるのではなく「国民の貧困化」とはっきり書くべきではないか? と思います。
デフレマインドと必勝の精神-日本に蔓延る大本営的な伝統
余談ですが日本のデフレマインドの解説、ないし日銀のデフレマインドのせい理論は、戦時中の必勝の精神理論を思い起こさせます。
まあ戦時中は物資生産がどうやったって追いつかなかったので、精神論で鼓舞するしかなかったのかもしれません。
しかし現代日本では、政府支出を拡大すればデフレは脱却できるのです。にもかかわらず「根強いデフレマインドが……」などと精神論に逃げるのは、知的劣化と言わざるを得ないでしょう。日本の経済エリートたちは、相当に頭が悪いようです。
……まあ頭が悪くないと、20年もデフレを続けません。20年もの長い期間にわたりデフレを継続させたのは、戦後では日本が唯一です。
麻生太郎大臣はかつて「景気は気の持ちよう」と言いましたが、デフレが精神論ではなく力学的なものというのは現代貨幣理論が明らかにするところです。
「デフレマインドに足を引っ張られて……」などという与太話の言説を、日本から一掃してしまいたいものです。