
最近、記事が冴えません。お仕事ハード。休み半年なし。プライベート何それ美味しいの? 超絶ブラック自営業(スタッフはブラックじゃない)のヤンです。
休みって、誰がくれるんだっけ?
時間がなくて、記事の構成が適当なので、記事が冴えないのです。
さて、プラグマティズムについて解説したいと思います。
プラグマティズムとは「理論と経験の両方から、物事を咀嚼すること」かと思います。
私の一番身近にある経験は料理です。料理を通して政治・経済を考えてみて、それを例に上げてプラグマティズムを理解してもらおう! という斬新で前衛的で、無茶な記事です(笑)
料理の本質と政治の本質
料理の本質って、なにか知ってます? 「食べてくれる人に、美味しく作ること」です。「ご馳走」という言葉があります。
これは「もてなすために、走り回っていろいろ集めたりする」ことだそうです。
ご馳走には「もてなす」という道徳的観点と、「走り回る」という行動的観点の2つが含まれます。
政治も一緒じゃないでしょうか? 「経世済民」という道徳的観点と、「それに向けた行動」という行動的観点の2つが必要です。
逆説的に「経世済民を謳うが、行動が伴わない」は、政治ではないのです。また、「経世済民ではないが、行動する」もまた、政治ではありません。
経済の本質と料理の本質
料理の本質は「美味しいものを食べてもらいたい、食べたい」です。技術や料理哲学などは、そのための方便です。料理は美味しかったら正義です。不味かったら悪です。
経済も同様です。
景気が良ければ正義であり、デフレや不景気は悪です。
理論なんかはどうでも良いのです。味覚と自我において、これは自明です。
どんな理論を唱えようと、まずい料理はまずいです。理論がいかに緻密であれ、まずいものはまずいのです。
主流派経済学は不味いですから、私は味を確かめて吐き出します。
プラグマティズムと味覚
プラグマティズムは味覚に似ています。
プラグマティズムは実践主義、実用主義と訳されます。経験主義ともいえるでしょう。対して味覚は?
味覚とは先天的なものと、後天的なものに分かれます。ニガウリやビールが美味しく感じたのは、いつからですか?
苦味とは毒を意味するので、先天的には嫌います。酸味は腐臭を意味しますので、これまた嫌います。
しかし後天的な経験を積むことで、苦味や酸味を「美味しい」と思うようになるのです。
拙い味覚では、美味しい料理も味わい尽くせません。美味しいものを美味しい! と判断できる舌こそが、プラグマティズムでは? と思います。
舌バカの蔓延る日本
安倍政権の支持率は、報道によると59%らしいです。舌バカの蔓延る日本です。
幼い頃からジャンクフードを食べていると、繊細な味はわからなくなります。ポテチやハンバーガーの「強烈な旨味」に、舌が慣らされるわけです。
今の日本人の姿でしょう。
しかし……希望はあります。若い人に出汁を引いた味噌汁を飲ませると、例外なく美味しいといいます。
鰹節で本枯は使えません。高いですから。そこそこのものです。味噌もスーパーで手に入る、最上のものです。
※というか、本枯を味噌汁に使ったら怒られますね(笑) 普通は吸い物にします。
旨い料理は、誰にとっても旨いはずです。記事で、主張で「示せるかどうか?」です。
自分の精通している分野で、物事を例えて理解しよう
私は料理以外に、あまりできることはありません。ライティング、SEO、WordPress関連などは……まあサブみたいなものです。
政治や経済を、自分の精通している分野で考えてみましょう。もちろん「国家経済と家計は異なる」という前提はお忘れなく。
政治や経済の話を実経験に落とし込むとき、ようやくプラグマティズムとなるでしょう。料理でいえば「腹に落ちる」料理ができるのです。
それ以外は「うわの空」です。
文章とは「理解」してないと書けません。どう理解するのか? プラグマティズムによって理解すればよいのではないか? と思います。
そして私でいえば、料理と同じように記事を書くのです。メニューを考え、使う材料を考え、それらを”料理”にしていく。
記事も一緒でしょう?
今日の記事も冴えません……(汗) 構成もせず、片手間に書いたにしては上々かも知れません。本日も労働ハードなり。
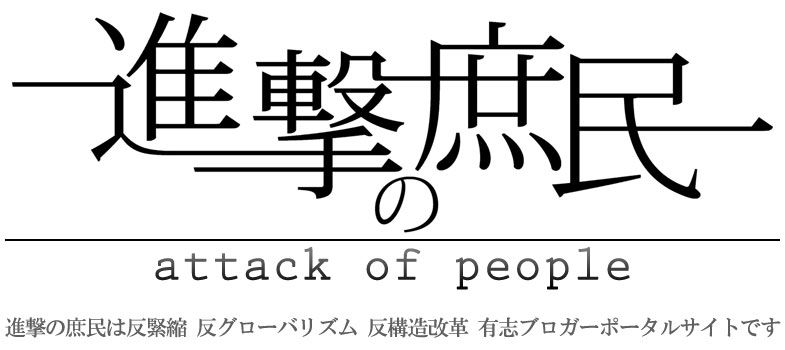


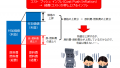
>プラグマティズムと味覚
上記を見て、そこからさらに発想して思いましたが・・、
ネット右翼や、旧式経済学の信奉者と言うのは・・、なんというか、『理屈っぽい』という印象をなんとなし、受けましたね。
現実ではなく、こうであるはずだという『理屈』でものを考えているというか・・。
ここ最近のこの界隈のコメント欄を見ますに、なんだかそういう印象を受けましたね。
理屈も大事だとは思うのですが、理屈の向こう側というのにも、気づく必要があるのではないかと思うのです。
理屈も大事だけど、理屈だけじゃないという・・、そのあんばいと言いますか・・、まあ、うまいこと言いづらいものがありますが・・、まあ、なんと言いますか、そんな感じの話です・・、すみません・・(^^;)
べき論、である論ですね。理想論と現実論、と言い換えても良いです。
理屈が通じないのが現実とするなら、理屈の向こう側があってしかるべきかも知れません。
おそらく理屈っぽいと感じるのは「べき論」だからじゃないでしょうか?
「愛国者である”べき”」「憲法は改正する”べき”」みたいな。
でも「べき論」は「である論」の後なんですよね。
「現実は(例えばMMTによれば)こうである」とか「自公が参院選を勝っても、憲法改正はされないのである」とか。
味覚って共同体内で、美味しい味は「自明――つまり常識――」だったりします。一つの「である論」なんですね。
※国によって、美味しい味付けが変わるのも面白い話です。
「である論」という現実の先にこそ、料理は幅広い個性やオリジナリティを持つのです。これが「プラグマティックなところ」じゃないかなと。
政治も「現実はこうである論」→「だからこうするべき論」という段階を踏まないと、理屈っぽくなるんじゃないかなと。
味覚で思いました。
小泉Jr.や橋下は味覚に訴えるのではなくて、視覚に惑わされてるだけに見える。
そういえば一時期政治の、見える化、視覚化、スケルトン化とかが流行ったような気がします。あれの最悪なるはマストが具現化した者が彼奴(きゃつら)のような気がします。マスコミはこぞって持ち上げるばかり。最悪なるはマストなマスコミ報道見える化?
失礼しました。
視覚ってコミュニケーションの、かなりの部分を占めているようです。言葉以外の要素が、コミュニケーションや訴えには、かなりはいってるんだそうで。
料理も見た目、味わい、匂い、温度などの要素が「美味しい」になります。
……問題は政治が「見た目」だけになっちゃっていることですね~。有権者も味や匂いに、鈍くなっちゃっているのかも知れません。